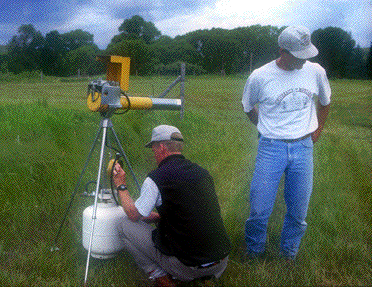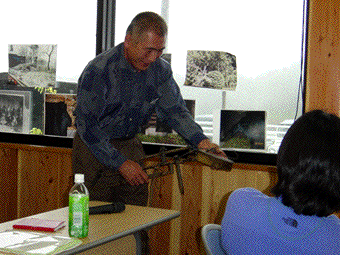Bear Gallery No.4
有限会社アウトバックはクマと人間との共存を模索した様々な活動を、国内と海外でおこなっています。
OUTBACK TRADING COMPANY LTD. does the various activities of searching
for coexistence with the bear and the human being in our country and
the foreign countries.
Gallery
1
/Gallery
2
/Gallery
3/
Gallery 4/ Gallery
5/
Gallery
6

「六角牛山(1,294m)の初冠雪」(2001年11月4日)
民話の古里、岩手県遠野市にある六角牛山は、ツキノワグマの大切な生息地でもある。
平成13年11月4日午前11頃、家族を四輪駆動車に乗せ、
遠野市周辺の林道をツーリングをしていたときに撮影した。

「岩手山を眺めながら一服」
快晴で風が吹かなければ、スノーシュー(洋式カンジキ)でのスノー・トレッキングは最高にハッピー!
この日は歩いている最中、暑くてTシャツ1枚でもオーケー。
ストックのバックに見えるのが、岩手の主峰岩手山(2049m)。
通称・裏岩手の雄姿を眺めながら、チョット一服。
(撮影日:2002年1月14日/撮影者:藤村正樹/デジタルカメラ:SONY
DSC-P5)

「今年の春は熊に注意!」
「熊に注意!」の看板は秋田県田代町で撮影したものです。
1992年6月1日、田代町ではクマに襲われ男性(64)が死亡しています。
死亡した男性は地元のハンターで、現場の山林を「庭」のように知り尽くした山のベテランでした。
タケノコを採っているときに親子グマに遭遇し、親グマに襲われたとみられています。
タケノコを入れたリュックの中にはナタもありましたが、取り出す間もなく襲われたのでしょう。
春は1年のうちで最もクマの事故が多い季節です。
北海道では平成13年の4月から5月にかけて、3人の方がヒグマに襲われて命を失っております。
岩手県でも同年の6月8日に、山菜採りに行った地元の男性(この方もハンター)がツキノワグマに襲われ死亡しています。
平成14年は暖冬暖春の影響で雪溶けも例年より早く、クマの事故が増える可能性も高くなっています。
山菜採りや渓流釣り、タケノコ採りなどで山に入る人は、クマに十分注意しましょう。
(撮影日:不明/撮影者:藤村正樹)
 "GARBAGE
KILLS BEARS"
"GARBAGE
KILLS BEARS"
イエローストーン国立公園(米国ワイオミング州)内に設置されているクマ対策ゴミ箱です。
アメリカ合衆国の法律では、国立公園及び国有林の中でクマに餌を与えることを禁じています。
生ゴミ(GARBAGE)のゴミバケツから、クマが勝手に餌を取ることも同様です。
人間にとってゴミでも、クマには簡単に手に入る美味しいご馳走です。
人間が捨てたゴミや空き缶・生ゴミに依存した(餌付いた)クマは、人に対する恐怖心が段々薄れていきます。
エサを求めて人里に出没したり、人家に上がり込んだり、人に危害を加えるようにもなります。
そのような「餌付け熊」(GARBAGE
BEAR)は危険なクマとして駆除されます。
人間が捨てたゴミが原因となって、多くのクマが殺されています。
生ゴミや空き缶、コンビニで買った弁当のゴミなどは、持ち込んだ人が必ず持ち帰りましょう。
(撮影日:2001年5月/撮影場所:米国イエローストーン国立公園/撮影者:藤村正樹)
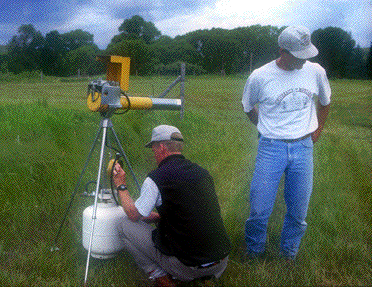 米国製爆音器
米国製爆音器
日本でも鳥や獣の追い払い用に爆音器が使用されているが、
これは米国モンタナ州のロッキー山脈の山麓で使用されている爆音器です。
ここでは主にグリズリーベアなどの追い払い用として使用されています。
この爆音器は日本と同様にプロパンガスを使用しています。
ただし、爆音が鳴るとヘッド部分が45度回転します。
それによって音が様々な方向から聞こえてくるので、獣の追い払い効果が持続します。
さらに、タイマーをセットすることによって、音の出る間隔を時間帯によって調整することができます。
写真に写っている2人は、モンタナ州政府野生動物保護管理局のグリズリーベア専門官です。
日本で一般的に使用されている爆音器は、同じ間隔で音を発生するだけなので、
獣や鳥は「音がしても安全」だと学習してしまい、、効果が持続しません。
(撮影場所:米国モンタナ州 撮影時期:1997年7月 撮影者:藤村正樹)

クマ頭部角器
この角で作られたクマ頭部角器は北海道常呂町で発掘された、オホーツク文化の遺物です。
リーダーの指揮棒のような役割を持っていたと考えられています。
オホーツク文化の遺跡からは、様々な動物を表現している遺物たくさんが発掘されていますが、
クマを表現したものは全体の40%ほどに達しています。
その多くは骨製ですが、角・牙・土・木製もあります。
参考文献:「北の異界 古代オホーツクと氷民文化」(西秋良宏/宇田川
洋・著 東京大学出版会)
(撮影場所:東京大学総合研究博物館 撮影時期:2002年6月 撮影者:藤村正樹)
 " Boat
Rafting of Montana "
" Boat
Rafting of Montana "
暑中お見舞い申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
太陽がギンギンに輝き、夏空のまぶしいこの頃ですが、
皆様のご健勝を心からお祈り申し上げます。
2002年 盛夏

" 元気いっぱい! 阿仁の子グマ達 "
マタギ発祥の地、秋田県北秋田郡阿仁町には、
ツキノワグマを約100頭飼育している阿仁町クマ牧場があります。
写真は平成14年2月に生まれた子グマ達です。
いかにも、いたずら好きなヤンチャボウズばかりです。
阿仁町クマ牧場は複数の大学の研究者や学生達に、実験や研究の場所を提供しています。
その研究者や学生さん達が集り、8月に阿仁町で行ったクマゼミ合宿に参加した時に撮影しました。
(撮影日:2002年8月10日 撮影者:藤村正樹/有限会社アウトバック)


"野生鳥獣管理者技術育成研修(クマ類) "
財団法人自然環境研究センター(理事長・多紀保彦)では環境省からの委託を受け、
主に自治体の野生鳥獣行政担当者を対象とした、「野生鳥獣管理技術者育成事業」を毎年実施しています。
そして、その一環として「自然地域における大型獣の保護管理」に関する研修を実施しており、
去る平成14年12月10日〜13日、岩手県盛岡市にて2002年度第1回野生鳥獣管理者技術者育成研修(クマ類)が開かれました。
写真は12日に行われた現地視察の時のものです。
12日の現地視察では、(独)森林総合研究所東北支所の三浦慎悟さんと岡輝樹さんの指導で、
実際に1頭のツキノワグマを追跡している現場に行き、テレメトリー調査の実習が行われました(写真左)。
次に、三浦慎悟さんと岡輝樹さんが行っているヘアートラップの調査地に移動し、
適地や注意点などについて説明された後に、ヘアートラップの設置方法についての実習が行われました。
ヘアートラップ調査とは、クマの誘引物(写真右)の周囲に有刺鉄線を設置し、誘引されたクマの体毛を採取する調査手法です。
採取された体毛のDNA分析によって、誘引されたクマの性別や個体識別、生息数の推定、同一個体の行動域など様々な学術的データを得ることが可能です。
その後、有限会社アウトバックの藤村正樹によって、熊撃退スプレーの使用法の説明と実習が行われました。
(撮影日:2002年12月12日 撮影者:藤村正樹/有限会社アウトバック)


"普及啓蒙活動と未来のクマ対策(?) "
今回は2つのイベントに関連した話題です。
左側の写真は、平成15年2月9日に東京都多摩動物公園で開催されました、
(財)東京動物園協会と日本クマネットワーク(代表・青井俊樹)とで行ったクマのイベントの一こまです。
浦幌ヒグマ調査会の若手クマ研究者グループが作成した「ヒグマの冬眠穴」(右端の黄色いドームテントのようなもの)に、
参加者に実際に入ってもらい、クマがどのような場所で冬眠しているのかを体験してもらいました。
実際にヒグマが冬眠した穴に研究者は入り、内部の寸法を計測し、それをリアルに再現しています。
特に子供達には好評で、2回3回と並んで入る子供もいました。
他にも様々なイベントが企画され、クマの生態や人とクマとの軋轢等について、多くの参加者に知っていただくことができました。
右側の写真は平成15年3月4日〜7日まで東京ビックサイトで開催された、"Security
Show 2003"で撮影したものです。
これは北九州市の株式会社テムザックが開発した、ホーム・ユーティリティ・ロボット「番竜」(BANRYU)です。
お話しをおうかがいした企画室長の古川真氏の話では、イノシシ対策に使えないかとの問い合わせが某大学の関係者から寄せられたそうです。
(撮影日:2003年02月09日、2003年03月13日 撮影者:藤村正樹/有限会社アウトバック)
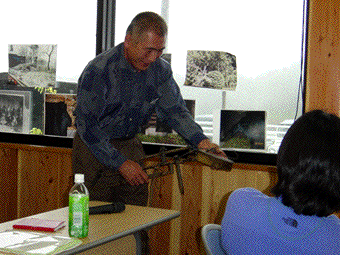

"第10回 『クマを語る集い』開催 "
平成15年5月31日、6月1日に、宮城県柴田郡村田町の宮城県クレー射撃場・狩猟者研修センターにて、
第10回「クマを語る集い」in蔵王の里・村田町が開催になり、北海道から福井県までの全国各地から約50名の参加者がありました。
第1日目は北蔵王の自然を守る会の丹野恵次さんから「蔵王山麓のに森と川とツキノワグマ」についての発表(写真右)や、
柴田郡猟友会会長の桜中良寿さんからは宮城県クレー射撃場ができたいきさつや周辺の狩猟について、
米国・モンタナ州立大学・生態学部野生動物保護管理コースを卒業された亀山明子さんからは、米国のクマの分布と生態・
クマ被害の状況やその対応の仕方・米国の狩猟制度などが紹介されました。
ツキノワグマの会の長谷川淳さんからは、栃木県足尾山で観察を続けている
ツキノワグマの素晴らしい映像が上映され、参加者は皆感銘を受けました。
特定非営利活動法人・野生生物保全研究会の戸川久美さんからは、国内における熊胆(ゆうたん/熊の胆)流通の実態について発表がありました。
2日目はツキノワと棲処の森を守る会の板垣悟さんが、クマに食べさせるデントコーン畑を地元のハンターと共同で耕作し、
他の畑の被害を未然に防ぐための試み(クマの畑)について発表や、
今回の実行委員長でもあるハンターの佐藤善幸さんから、くくり罠による錯誤捕獲の問題などが実演を交えて(写真左)発表があり、
最後に岩手県ツキノワグマ研究会の藤村正樹より、クマを語る集いを平成5年から開催し続けているいきさつや、
この10年間のクマの保護や被害対策、狩猟法の改正、今後の課題などが発表されました。
なお、「クマを語る集い」(旧日本ツキノワグマ集会)は宮城県のツキノワと棲処を守る会と、
岩手県の岩手県ツキノワグマ研究会が交互に実行委員会を担当し、
1993年からほぼ毎年開催しているクマと人との共存について考える集まりです。
(撮影日:2003年05月31日、2003年06月01日 撮影者:藤村正樹/有限会社アウトバック)
注意事項
ここに掲載された画像ファイルを、当社の許可無く複製、掲載、出版、
放送等の二次使用をすることは禁止します。
当社で制作したものに限り、すべての著作権は
有限会社アウトバックに帰属します。二次使用を希望される方は当社までお問い合せください。
日本クマネットワーク(JBN)会員による、教育や学術目的、あるいは公共的目的に限定した複製や二次使用を認めます。ただし、事前にご連絡下さい。
また、本情報に基づいた行為にお
いて発生したいかなる人物の負傷、死亡、物品の損失、損害に対する全ての求償の責は負いかねます。
Copyright 2001. OUTBACK TRADING COMPANY LTD.
No reproduction or republication without written permission.
(有)アウトバック
〒020-0401 岩手県盛岡市手代森16-27-1
TEL:019-696-4647 FAX:019-696-4678
outback@cup.com