 相互リンクについて (バナーはこちらにあります)
相互リンクについて (バナーはこちらにあります) ![]() お知らせ
お知らせ
![]() クマ関連のリンク集
クマ関連のリンク集
![]() 野生動物 &
自然系リンク集 (クマ以外の野生生物や自然、その他)
野生動物 &
自然系リンク集 (クマ以外の野生生物や自然、その他)
![]() マタギ関連のコーナー(田口洋美さんの作品紹介) (作家、マタギ研究者、狩猟文化研究所 代表
田口洋美さんの作品を紹介します)
マタギ関連のコーナー(田口洋美さんの作品紹介) (作家、マタギ研究者、狩猟文化研究所 代表
田口洋美さんの作品を紹介します)
![]() 斎藤 純さんの作品紹介 (作家、エッセイストの斎藤純さんの作品を紹介します)
斎藤 純さんの作品紹介 (作家、エッセイストの斎藤純さんの作品を紹介します)
![]() 熊谷達也さんの作品紹介 (民族学会やクマ研究者からも注目されているノンフィクション作家、熊谷達也さんの作品を紹介します)
熊谷達也さんの作品紹介 (民族学会やクマ研究者からも注目されているノンフィクション作家、熊谷達也さんの作品を紹介します)
![]() 野生動物写真家の原田純夫さんの作品紹介
野生動物写真家の原田純夫さんの作品紹介
![]() その他のウェブサイト (何が出るかは見てからのお楽しみ!?)
その他のウェブサイト (何が出るかは見てからのお楽しみ!?)
![]() アウトドア関連リンク集
アウトドア関連リンク集
![]() アカデミー系リンク集 (野生動物関連学会のサイトなど)
アカデミー系リンク集 (野生動物関連学会のサイトなど)
![]() Y2K(コンピューター2000年)問題リンク集
Y2K(コンピューター2000年)問題リンク集
 相互リンクについて (バナーはこちらにあります)
相互リンクについて (バナーはこちらにあります)
![]() リンク&お知らせ
リンク&お知らせ
●鳥獣保護法「改正」に関連するシンポジウム報告書販売のお知らせ
●インドネシアのカリマンタンから”オラウータンの森を山火事から助けて欲しい”という緊急の救援要請が発信されています。
簡単な説明はこちらをご覧下さい。
●『クマ本ライブラリー』をオープンしました(蔵書数97冊)。
●マタギ関連
●叉鬼山刀について紹介している書籍
●マタギと狩猟文化の研究者・田口洋美氏(日本狩猟文化研究所代表)の著作紹介
トップに戻る
![]() クマ関連のリンク集
クマ関連のリンク集
●一部を除き、ここでご紹介しているウェブサイトとは相互リンクをしています。
|
|
|
|

|
|
・クマと遭遇したときは
(クマに出会わない方法、クマを引き寄せない方法、クマに出会ったときの対処法、クマの追い払い法など)
|
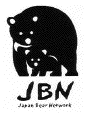 日本クマネットワーク(JBN) |
|
日本全国の主なクマ研究者が中心となって運営している民間団体。入会(有料)すると年4回のニュースレターとメーリングリスト参加などのサービスを受けることができます。 |
|
|
子供向けにクマについて紹介しているウェブサイト。子供向けに分かりやすい英語で書かれているので、日本人でも理解できるでしょう。(ENGLISH) | |
|
|
奥多摩ツキノワグマ研究グループの活動と、奥多摩に生息している、東京の野生ツキノワグマを紹介します。多摩動物公園で開催している特別展「東京の野生動物 ツキノワグマ」の情報も掲載しています。 | |
|
|
岡山県内に生息するツキノワグマは、環境庁のレッドデーターブックで「東中国山地地域個体群」に位置づけられ、「絶滅の恐れのある地域個体群」に指定されています。平成12年11月に岡山県英田郡西粟倉村で開催された岡山県ツキノワグマフォーラムの公式サイトです。 | |
|
|
http://www.geocities.jp/shinshukumaken/
|
同研究会の活動を紹介しているHP。捕獲放逐、ドラム缶罠、お仕置きについても、写真入りで詳しく紹介しています。 2003年8月にウェブページが新しくなりました。 |
|
|
東京大学秩父演習林でツキノワグマの調査を行っている石田健氏のホームページです。ミズナラ堅果の結実特性の遺伝や、秩父のツキノワグマについて紹介しています。 | |
|
|
野生動物と人との共存を目指して、ツキノワグマをはじめ、様々な野生動物の講演会や観察会、啓蒙普及活動を行っているNGOです。 | |
|
|
|
The International Association for Bear
Research and Management (IBA)
はクマの研究と情報を普及啓発するための、世界中のクマ研究者が参加している国際的な民間団体です。 |
|
|
|
クマの生態や世界各地に生息しているクマを紹介しています。(English) |
|
|
クマに関連するホームページ・リンク集。(English) | |
|
|
http://www.muratasystem.or.jp/‾kukuma/shiretoko/i-real/r-death/r-k0821.htm |
知床の自然を紹介するHP。知床の番屋を荒らした結果、有害鳥獣駆除されたヒグマの写真が載っています。原因は人間が捨てた缶ジュースではないかと見られています。人間が捨てた生ゴミや缶ジュースの味を覚えてクマは、だんだん人里に接近し、人間の怖さを忘れ、家に上がり込んだり、農作物を荒らしたり、人を傷つけたりするようになり、最後は有害鳥獣駆除で殺されます。非は人間にあります。 |
|
|
ツキノワの生態が分かりやすく紹介されています。 | |
|
|
「鳥獣及び狩猟に関する法律」の法改正についてのホームページ。 | |
|
|
広島市安佐動物公園の獣医士、大丸 秀士氏のホームページです。レッサーパンダの赤ちゃんの声が聞けるし、日本動物園水族館協会加盟の160もの園館にもリンクしています。動物園で働きたい人、動物園に興味のある人はぜひご覧ください。とくに{「ゆるす」人々==ツキノワグマの話(96.01.04)}http://www.asahi-net.or.jp/‾rn2h-dimr/ohanasi/kuma960104.htmlをぜひご一読ください。 | |
|
|
|
北海道に生息する野生動物の調査、研究をしています。 |
|
|
|
1996年からテディベアを作り始めたフーズベアの工房は標高1.500メートル、信州は八ヶ岳の麓にあります。自然を題材にしたベアが特徴です。この地で生まれる熊達の中には森のエッセンス(木曽檜)が詰めてあるので、抱きしめると心地よい香りがします。どうぞ末永く可愛がってあげてください。 |
|
|
ヒグマとの共存を目的としたヒグマ紙芝居の絵が載りました。ほかにも、悪質なサケマス釣りによって、ヒグマが誘引されている問題や、斜里町内98-99オオワシ・オジロワシ保護状況(鉛中毒発生状況)の情報などが紹介されています。ワタリガラスに関する情報も載っています。 | |
|
|
主なコンテンツは「オーストラリア・パース カンガルー日和」と「カナダ・ロッキーのベージ 」です。後者にはウェブ・オーナーがロッキー山脈を旅して実際に見た、クマやエルク、マウンテン・ゴートなどの野生動物が紹介されています。デナリ国立公園のページには、グリズリーベアの親子の写真が6枚アップされています。 | |
|
|
http://www.city.akita.akita.jp/city/in/zo/map/sohgo/kuma.htm |
秋田県秋田市の大森山動物園に飼育されているツキノワグマの説明。 |
|
|
http://www.age.ne.jp/x/toriumi/hoshino/h_cont.htm (ウェブサイト) |
星野道夫さんのお導きで知り合った、星野道夫氏を信奉され、彼の作品などを紹介しているサイトを主宰している鳥海さんのホームページです。星野さんの作品や、彼に対する思いなどがつづられています。尚、鳥海さんの掲示板( BBS)には大阪圏でのクマ出没情報や、星野道夫さん関連情報が毎日のように掲載されていますよ。 |
|
|
よこはま動物公園(ズーラシア)園長・増井光子さんの随筆「ミレニアム新動物園記」に、ズーラシアで飼育されている3種類のクマの話「植物に興味津津のメガネグマ」が載っています。南米に生息しているメガネグマの写真も掲載。 | |
|
|
|
獣害とは、野生動物による人間への害と、人間による野生動物への害の双方を指します。 |
|
|
福岡県在住の野生動物写真家・栗原智昭さんのホームページです。彼は今、絶滅したとも言われている、九州のツキノワグマの撮影に取り組んでいます。栗原さんの苦労談や、自動撮影カメラのこと、秘蔵の写真などが紹介されています。 |
|
福井県自然保護センター |
http://www.erc.pref.fukui.jp/gbank/reports/ciconia/linklist/list.html |
CICONIA (福井県自然保護センター)の研究報告の総目録が載っています。クマに関するデータは次の通りでした。「福井県におけるツキノワグマの生息環境と分布 −1990〜1996年」、「福井県におけるツキノワグマの生息個体数の推定 −1991〜1995年度」、「福井県におけるツキノワグマの捕獲個体数の経年変化」、「4-8 福井県におけるツキノワグマの捕獲および出現状況 −1990年度〜1993年度」、「福井県におけるツキノワグマの行動圏と環境利用」 |
|
特命リサーチ200X! (日本テレビ) |
日本テレビ系で放送中の「特命リサーチ200X!」のサイト。番組の中で「極東調査会社」が調査した自然現象や超常現象、生命の不可思議・・・等々のデータが紹介されています。その中には、「熊に襲われない方法」(2000/06/18放送)も載っていました。実は、弊社も情報提供やクマ避けグッズの貸出などで、番組制作に協力しました。 | |
|
|
小学校の先生である漆山仁志さんが運営する「教育実践ホームページ」に、『「山をすてたクマ」の授業』というタイトルの、総合的な学習の時間(環境)と関連づけて指導すると効果があがる、クマをテーマにした授業プランが紹介されています。「農作物を荒らしたり、町に出てきたツキノワグマを射ち殺すことを許せるか」というテーマで、小学生がクラスで討論するところから始まります。とても興味深い内容ですので是非ご一読ください。 | |
|
|
http://www.city.sapporo.jp/kankyo/ryokuka/HOZEN/kuma/hyousi.htm |
北海道札幌市はインターネットで平成9年から現在までのヒグマ出没情報を公表しています。公開されているのはクマの目撃や出没(痕跡)などの情報です。特に2001年5月は札幌市内の定山渓で、山菜採りの男性がヒグマの襲われ死亡するという痛ましい事故が発生しています。札幌市に行かれる方は、札幌市役所のサイトを事前に確認されることをお薦めいたします。 |
|
シロクマ紀行 |
|
極北の地で生活するホッキョクグマに魅せられた動物写真家のHisashi Okadaサンのサイトです。カナダ極北にあるチャーチル(ホッキョクグマの集まる町としてとても有名)での5年目になる白熊の写真撮影と、そのノンフィクション物語で構成されています。写真も3万枚を超え、7回目の取材と写真撮影の準備中とのことです。とにかく素晴らしい写真がたくさん載っているし、雄のホッキョクグマが母子グマを襲う場面など、手に汗握る感動のエッセイ等オススメのコンテンツです。ぜひご覧下さい。 |
|
|
札幌市教育委員会が設置し、財団法人札幌市青少年婦人活動協会が管理運営している定山渓自然の村(自然体験型の施設)のサイトです。ヒグマの生態やトラブル回避の知識などを詳しく紹介しています。ヒグマは前足で、2センチの鉄筋を簡単に曲げてしまうほどの力があり、時速60kmの車と一緒に20分間も走り続けた等の記録があるそうです! なお、当社のサイトとリンクしています。 | |
|
|
http://www.pref.miyagi.jp/sizenhogo/tyoujyuhogohan/kuma/kuma.htm |
宮城県自然保護課のクマ情報のサイトです。クマ出没情報、クマに出会わないためのヒント、クマに遭遇した場合の対処法などを紹介しています。 |
|
(株)野生動物保護管理事務所 |
|
[Wildlife Management]とは、「野生動物」と「人間」と「生息環境」の3者の関係を調整する科学的な技術です。民間の野生動物調査会社である野生動物保護管理事務所(WMO)は、日本の野生動物とその生息環境を護っていくうえで、とても大切な企業であり野生動物研究者の集団でもあります。また、人材育成の場にもなっているので、野生動物の調査研究を目指している若者は、ぜひWMOのドアをノックしてみてください。WMO clubという会員制のクラブには、一般の方も参加できます。 |
|
PHOTOGRAPY ONLINE |
野生動物写真家David B. Jack氏のサイトです。平成13年6月に知床国立公園で実際にヒグマに襲われ、カウンターアソールトでそれを追い払ったときのレポートや、たくさんのヒグマの写真などが載っています。 | |
|
|
北海道日高町のホームページに掲載されている、ヒグマに出会わない、遭遇しないための注意事項や、遭遇しておさわれた場合の対処法について書かれています。 | |
|
|
大雪山登山者のための様々な情報や、注意事項が掲載されています。その中に、ヒグマに出会わないための注意事項や、ヒグマの出会ってしまったときの注意事項が載っています。 | |
|
非公式サイト |
岐阜大学ツキノワグマ研究会OBの吉田さんが運営しているクマのウェブページです。 | |
|
|
1996年に設立された民間団体、東中国クマ集会のホームページです。関西を中心に積極的な活動をしています。 | |
|
|
|
森林総合研究所は森林を総合的に研究する日本で唯一の研究機関です。クマをはじめ様々な野生動物の調査研究も行っています。 |
|
|
|
野生動物写真家の前川貴行さんのホームページです。ホッキョクグマやグリズリーベア、ハクトウワシ、ニホンザルなどを撮影した素晴らしい作品が多数掲載されています。その他にも前川さんの日記や、絵本・ポストカードなの殿作品も紹介されています。 |
|
|
|
「林用軌道解体新書・秘境探検」は、長野営林局と名古屋営林局の林用軌道を紹介するウェブページですが、長野県、岐阜県、群馬県、新潟県などのツキノワグマ情報も掲載しています。この方面に行かれる方はぜひご覧下さい。 |
|
|
2003年9月にリニューアルした岐阜大学ツキノワグマ研究会の公式サイト。メンバーの紹介や活動紹介、クマハギの写真、掲示板があるとても楽しい(?)ウェブページです。相互リンクしています。 | |
|
|
http://www.muratasystem.or.jp/‾rausu/j/nature/kuma/fr-contents01.html |
羅臼町のウェブページに載っている、「ヒグマに対していかに行動すればいいのか」です。 |
|
四国自然史科学研究センター |
|
絶滅の危機に瀕している四国ツキノワグマの保護活動も行っている民間団体です。自動撮影装置による貴重な四国ツキノワグマの撮影に成功しています。その画像はウェブページで公開されています。 |
|
|
長野県森林保全課のウェブページに、クマによる事故を防ぐための情報「ツキノワグマによる人身被害を防ぎましょう」が掲載されています。掲載されている画像の中に、当社の南部熊鈴も写っていますので、ぜひご覧下さい。 | |
|
(白化ツキノワグマの展示) |
http://www.museum.city.nagaoka.niigata.jp/labo/animal/animal.html |
新潟県の長岡市立科学博物館では貴重な白化ツキノワグマ(ツキノワグマのアルビノ)の剥製を展示しています。同館動物研究室のウェブページには、1977年11月6日に新潟県中蒲原郡村松町で捕獲された白化ツキノワグマ(雌・成獣)の画像(剥製)が公開されています。 |
|
『ツキノワグマによる被害を防ぐために』 |
http://www011.upp.so-net.ne.jp/shinshu_kumaken/nagano/nagano-index.html |
長野県長野市では、平成10年頃より市内北部のほぼ全域でツキノワグマが出没するようになり、トウモロコシ、リンゴ、プルーン、養蜂等の被害が出始めました。平成12年以降は、市内山間部全域で出没するようになり、農業被害は毎年6月頃から長野市北部の地域を中心に発生し、出没・被害情報が年間20件以上寄せられるようになってきています。 |
|
|
http://shiretoko.muratasystem.or.jp/1998/98bear/980804a.html |
平成10年(1998年)8月 斜里町自然保護係・知床自然センター管理事務所が作成した、知床半島のヒグマの情報と安全対策について掲載されています。 |
|
|
http://www.shiretoko.or.jp/ZAIDAN.HTM |
ヒグマやエゾジカの保護管理・調査・研究を含め知床国立公園を中心に知床の自然を人々に伝える活動を行っている財団法人です。なお、有限会社アウトバックは財団法人知床財団の団体会員です。 |
|
|
http://www.pref.kyoto.jp/forest/alacarte/nakama/kuma/kuma.htm |
京都府森林保全課のウェブページです。ツキノワグマに関しての情報が掲示されています。 |
|
ツキノワグマによる農業被害を防ぐために |
長野県のウェブページです。ツキノワグマによる農業被害を防ぐための情報が載っています。 | |
|
ツキノワグマ保護管理計画 |
長野県のツキノワグマの推定生息数は1,300頭〜2,500頭です。ツキノワグマの地域個体群を安定的に維持しつつ、人身被害の回避及び農林業被害の軽減を図り、人との共存を図ることを目的として、平成14年度に特定鳥獣保護管理計画(ツキノワグマ)を策定しています。このウェブページでは長野県が策定した特定鳥獣保護管理計画(ツキノワグマ)について紹介されています。 | |
|
|
北海道渡島支庁が制作した渡島半島地域のヒグマに関する普及啓発を目的としたとても素晴らしいウェブページです。ヒグマの生態や渡島半島の人々との関わり、被害問題、電気柵や熊避け鈴・ゴミ対策や下草刈りなどの被害防除策、その他にもたくさんのヒグマに関した情報が、画像やイラスト、図表、動画などで表現されています。日本国内のクマ関連のウェブページでは、最も優れたコンテンツと表現しても過言ではありません。ぜひご覧下さい。 | |
 |
http://www.oshima.pref.hokkaido.jp/os-ksktu/kuma/kids/index.html |
北海道渡島支庁 地域政策部環境生活課自然環境係のウェブページで公開されている、ヒグマの生態や人との関わり、被害問題、被害防除策などについてとても分かりやすく説明されている電子紙芝居です。子供向けとかかれてありますが、大人も十分勉強になる、とても素晴らしいコンテンツです。御覧になるにはMacromediaのFlash Player6が必要です。 |
|
|
秋田県のウェブページには、クマ出没情報やヤマビルの防除方法などの情報が掲載されています。 | |
|
|
http://www.muratasystem.or.jp/‾rausu/j/nature/kuma/fr-contents01.html |
知床公立公園に隣接する羅臼町では、毎年ヒグマが出没しています。羅臼町役場のウェブページには、ヒグマに遭遇しないためのアドバイスや、ヒグマに遭遇した場合の対処の仕方についての情報を掲載しています。その中で当社の熊撃退スプレー「カウンターアソールト」が紹介されていました。 |
 特定非営利活動法人ピッキオ 特定非営利活動法人ピッキオ |
|
特定非営利活動法人ピッキオ(長野県軽井沢町)のウェブページです。NPO法人ピッキオでは、ツキノワグマやニホンザル、シカなどの調査研究と被害対策の活動や、浅間山山麓全体の地域生態系保全と生物多様性維持の活動、地域住民への普及啓発活動窓を行っています。そして、2004年からは、米国の民間団体Wind River Bear Instituteの指導の元に、日本で初めてのクマ対策犬「カレリアン・ベアドッグ」によるクマ対策に取り組みます。詳細はNPOピッキオのウェブページをご覧下さい。相互リンクしています。 |
|
|
福井県自然保護センターのウェブページです。1977年に発行された『大型野生動物生息動態調査報告書〜ツキノワグマ』が公開されています。 | |
|
尾瀬を中心に片品村の象徴ともいえる日本百名山の至仏山、武尊山、日光白根山の登山情報や生物の紹介をしているウェブページです。その中でこのページは、ツキノワグマの生態や痕跡及び成体の画像を掲載しています。 | |
|
|
学生時代、ヒグマ、エゾシカの生態を調べに北海道の山々を歩き回った代表の橋田真澄さんが、2003年より各地で子どものどうぶつ教室、野生動物講座、ネイチャーツアーを企画するために立ち上げた民間団体です。ヒグマと正しく付き合うための様々な活動を行っています。 | |
|
|
|
社団法人岩手県猟友会のウェブページです。岩手県猟友会では岩手県が行っている様々な野生動物の調査に協力しており、平成16年度はツキノワグマの狩猟の自粛を決定しています。 |
|
|
野生動物の専門家が運営しているツキノワグマの痕跡を集めたウェブページです。「ツキノワグマに出会いたい人も、出会いたくない人にとってもツキノワグマの痕跡を知ることはツキノワグマの生態をより深く理解する上で重要です。また、被害回避や安全確保の上でも痕跡の正確な判別は必要です。」とトップページに書かれています。痕跡の他にも、ラジオテレメトリー調査や被害防除策についても、詳しい情報が掲載されています。ぜひご覧下さい。 | |
|
|
|
山梨県内の熊目撃情報・熊出没マップの他にも、山梨県の観光案内・山梨の美味しいお店など、山梨の情報を掲載しているウェブページです。相互リンクしています。 |
|
|
|
(財)知床財団が運営している知床自然センターは、雄大で貴重な知床国立公園の自然や野生動物の生態を紹介するビジターセンターです。ぜひお立ち寄り下さい。なお、当社は(財)知床財団の活動をサポートしております。 |
|
クマによる事故を防止する案内 |
石川県環境安全部自然保護課のウェブページに、「ツキノワグマによる人身被害防止のために」が掲載されています。「引き寄せないために」「遭遇しないために」「遭遇してしまったら」の状況別に分けて注意事項が書かれています。その他にも、県民の疑問対して分かりやすく回答しているQ&Aのコーナーや、ツキノワグマの生態なども、一般の方にも分かりやすく紹介されています。石川県特定鳥獣保護管理計画もPDFファイルで閲覧できるのでぜひご覧下さい。 | |
|
クマに関する情報 |
富山県生活環境部自然保護課のウェブページでは、クマ対処法やクマの目撃情報(日付、場所、状況)、痕跡の画像等が掲載されています。 | |
|
|
滋賀県自然環境保全課のウェブページには、(1)ツキノワグマから身を守るために (2)県内のツキノワグマの出没状況とその対応について の情報が掲載されています。滋賀県は広報車用のテープを作成したり、各市町村や各学校などに1万枚ものチラシを配布するなど、積極的に啓蒙普及に取り組まれているの素晴らしいと思います。 | |
|
トラフィック
イーストアジア ジャパン |
|
WWFジャパンの野生生物取引調査部門を兼ねているトラフィック イーストアジア ジャパンが、クマの生態や里への出没や人身被害の原因、国際的にも問題になっている熊胆(クマノイ)の取引の問題などを分かりやすく解説したウェブページです。相互リンクしています。 |
|
|
くまだなの会は広葉樹の植樹など紀伊半島の豊かな生態系の保全に努め、野生生物と共存共栄をめざす数々の取り組みをしているNGOです。手作りの紙芝居や、DVD映像を題材にして、こども自然教室を全国で開講したり、和歌山県に保護され紀伊山地野生鳥獣保護の会が飼育しているツキノワグマの飼育舎の清掃ボランティア、ドングリの苗木を育てるなど多彩な活動を行っています。相互リンクしています。 | |
|
|
岩手大学生の有志が運営する同好会のウェブページです。コンテンツはまだすくないのですが、今後に期待しています。相互リンクしています。 |
|
|
|
|
|
(財)世界自然保護基金ジャパン (WWFジャパン) |
|
国際的な自然保護NGOのWWFジャパンのHP。WWFJの助成事業として、たくさんのクマ研究団体の活動が、これまでに援助を受けています。21世紀を担う子供達に、生きている地球を引きつぐための「2000年キャンペーン展開中」・他 |
|
|
|
|
|
|
|
美ヶ原の日替わり映像、日本野鳥の会軽井沢町支部のホームページ、日本初のコウモリ専門研究法人『東洋蝙蝠研究所』や信州のコウモリ情報など、貴重な情報が満載の橋本肇氏のホームページです。知られざるコウモリの生態などが紹介されています。 |
|
|
|
毎年莫大な養蜂被害を発生させるクマは、養蜂家にとってはとても困った生物です。リンドウの生産で有名な岩手県安代町で長年養蜂業を営む(有)角舘養蜂場のホームページです。不思議なミツバチの生態の紹介、蜂蜜の通信販売も行っています。当ホームページと相互リンクをしています。 |
|
|
|
獣医師と動物愛好家のコミュニケーションを目的とした、動物好きは必見のホームページです。プロの獣医さんがアドバイスしてくれたり、動物愛好家のBBSがあります。当ホームページと相互リンクをしています。 |
|
|
雷鳥にこだわったSekkyさんのホームページです。絶滅の危機に瀕している雷鳥についての情報が満載です。当ホームページと相互リンクをしています。 | |
|
|
|
(財)日本ユニセフ協会では、紛争に巻き込まれたコソボの25万人を越える子供達の救援活動を行っております。 |
|
|
動物学リソース(Zoological Resourse on
the WEB) | |
|
|
|
平成12年1月からサル・猫・あらいぐま・きつね・スカンクの入国時とサルを除くこれらの動物の出国時に検査が必要となります。その他、移入種の問題など。 |
|
|
|
有限会社 ジオ・ブレーンのホームページです。ここはDTPで製作される書籍に挿入するイラスト・地図・表などを、Macによってトレスしている会社です。(社)農山漁村文化協会から出版になった「活かして防ぐクマの害」(米田一彦・著)も担当され、それがご縁で相互リンクを貼りました。勝手に応援のページにはこれまでに手がけてきた書籍などが紹介されています。 |
|
栗原のホームページ |
|
野生生物メーリングリストで知り合った、福岡県在住の野生動物写真家・栗原智昭さんのホームページです。なんと、彼はアフリカの国立公園で環境教育官や野生生物調査官として勤めていたことがあるんですよ。栗原さんの撮影したアフリカや九州の野生動物の写真や、彼の書いたアフリカを舞台にした素敵な小説、アフリカ情報(サファリ入門 サファリ・国立公園情報 マラウィ生活情報)が満載です。 |
|
|
|
環境省の公式ホームページです。様々な情報が提供されています。 |
|
|
|
飯豊朝日山岳遭難対策委員会山岳救助隊中央班長が飯豊連峰と朝日連峰における安全で快適で感動のある山行を願い作成したウェブサイトです。運営者の井上邦彦氏は”昭文社エアリアマップ飯豊山”の執筆者です。 |
|
|
|
東邦大学の理学部生物学科で学ばれている、熊が大好きなhanaさんのホームページです。環境教育の活動もしています。ウェブサイトにはカワイらしいイラストが満載です。 |
|
|
|
超多忙生物学科学生のhanaさんが、米国カルフォルニア州のREDWOOD NATIONAL PARKに行ってきました。そこでの素晴らしい体験が、デジタル画像と一緒に紹介されています。hanaさんのお話では、REDWOOD NPにもブラックベアが生息しているそうです。 |
|
|
|
MATSUさんが運営している[情報調達名人]は、動物、検索エンジン、美容・健康、レジャー、食べ物、暮らし、子供、カルチャー、コンピューター、ファッション、ビジネス・・・など、様々なジャンルのリンク集ホームページです。 |
|
|
|
ぷりマミーさんが運営する、ぷりぷり山荘のウェブサイトです。尾瀬, 武尊, 秩父・奥秩父・奥多摩, 上信越高原の高山植物の紹介やルート情報、様々な尾瀬の情報を紹介する尾瀬写真館、掲示板、リンク集など見所が満載です。美しい画像に圧倒されますよ! |
|
|
|
岩手県の公式ホームページ。県政への提言とか議会便りなどハードから、岩手の自然や観光、人々の暮らし、産業、文化など様々なジャンルを網羅しています。岩手山火山防災マップ、火山観察情報なども公開していますよ。皆さんの県のウェブサイトと比べてみてはいかがでしょうか。岩手県は頑張っているなと思いました。 |
|
アウトドア&フィッシング |
|
カリフォルニアを中心にアメリカ西海岸の国立公園などのフィッシング&アニマルウォッチング等のアウトドア ガイド&情報を提供している、『カリフォルニア アウトドア&フィッシング』のウェブサイトです。 東京農業大学の野生生物同好会のOBが村上さんが運営していますので、全部日本語ですよ。相互リンクをすることになりました。 |

|
|
渓流釣り倶楽部「渓道楽」会長 田中邦彦さんのホームページです。釣り好きは必見ですよ。ユニークな釣りの仕方。知られざる穴場情報が紹介されています。相互リンクさせていただきました。 |
|
|
|
i-modeでも利用できる、べんりな検索サイト「特ダネクーポン」です。 全国での利用者が1000万人をこえるi-modeは今や、「遊ぶ」「食べる」「泊る」などのスポットを探すひとつの手段となりつつあります。(特に出張先や旅行先では便利!)そこで、全国のサービス業の皆様、御社のお店や施設をi-modeで宣伝しませんか?登録料は無料です。面白い情報が載っていますので、ぜひ一度覗いてください。弊社のウェブサイトと相互リンクさせていただきました。 |
|
|
アニメーションと鉄道情報が満載のウェブサイトです。え、クマはどこにいるかって?それは見てからのお楽しみ。素敵なアニメーションや全国の駅弁情報などが満載です。 | |
|
|
山形の野生動物を考える会の鹿俣さんが管理運営をしている、里山の自然と野生動物の仮想観察フィールドを中心としたウェブサイトです。里山に生息する野生動物たちの観察レポートや、足跡やロボットカメラで撮影した写真など、興味深い内容がたくさん紹介されています。 | |
|
|
|
岩手県自然保護課のウェブサイトです。岩手県が平成12年12月19日に発表した「希少野生生物種リスト」(岩手県版レッドリスト)や、「山 で ク マ に 遭 わ な い た め に !」、岩手山の自然を紹介している「岩手山便り」、その他県内の自然の情報がたくさん紹介されています。 |
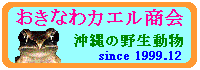 |
|
日本国内に生息する5科38種5亜種のカエルの内、実に約半数の5科20種が沖縄に生息しています。沖縄での大学在学中に、すっかりカエルの魅力にとりつかれた小原氏のウェブサイトでは、不思議なカエルの生態や魅力などについて、数多くの写真(プロ顔負けの凄い写真ばかり!)で紹介しています。その他にも、沖縄に生息する野生動物(写真も多数アップしています)やヤンバルの紹介、絶滅のおそれのある野生動物たちについての情報など、素晴らしいコンテンツがたくさん含まれています。ぜひご覧下さい。ただし、「おきなわカエル商会」ではカエルの販売はしておりません。沖縄のカエルを紹介・・・をもじって付けたネーミングだと言うことです。カエルの生息環境は悪化しつつあるので、カエルの保護を訴えるためにも、このウェブサイトを開設したそうです。 |
|
|
|
日本の自然保護活動の草分け的存在、財団法人日本自然保護協会の公式サイトです。平成13年から、インターネットでも手軽に寄付ができる”投げ銭サイト”が新しく始まりました。 |
|
|
|
林の中などに生息し、野生動物や人などに取り付いて吸血するヤマビル(陸生のヒル)の生態や、その対策などを紹介している「ヤマビル研究会」のウェブサイトと相互リンクしました。ヤマビルの他にもツツガムシやダニなど困った虫の情報も掲載されています。 |
|
|
|
「長良川河口堰建設をやめさせる市民会議」は、 1992年の“国際ダムサミットin長良川”を期して、 長良川河口堰に反対する旧新の59団体が集合して作ったNGOです。代表は、「長良川河口堰建設に反対する会」事務局長でアウトドアライターの天野礼子さん。長良川河口堰問題をはじめ、日本各地や世界のダム建設問題に関する情報が掲載されています。 |
|
|
今の日本が抱える多くの環境問題のなかで、生物の「種の多様性」に焦点を絞り、調査、情報収集、提言活動などに取り組んでいる市民団体「生物多様性研究会」のウェブサイトです。釣り場や里山の生き物といった、身近な自然の現状に目を向けて活動を行っています。 | |
|
|
|
社団法人エゾシカ協会(会長:大泰司紀之)のホームページでは、エゾジカの有効利用に関した情報(食材として、シカ肉の料理方法)、ハンティング・マニュアル(鹿肉に商品価値をもたせるためのマニュアル)、道庁が策定・実施しているシカの保護管理等の情報(北海道庁「エゾシカ保護管理計画」、北海道庁「ワシ類の鉛中毒対策について」、北海道庁「道東地域エゾシカ保護管理計画」)などが紹介されています。 |
|
|
|
All About Japanは、米国で2300万人が利用するabout.comの日本版サービスです。「ガイド」と呼ばれるその分野のスペシャリストが、自ら運営する「ガイドサイト」を通してユーザーをナビゲートしていので、ユーザーは欲しい情報を「詳しい人に聞く」ような感覚で、すばやく入手することができます。 |
|
|
|
「春夏秋冬おさんぽ雑記」は群馬県桐生市在住の主婦 坂井さんが趣味で運営しているウェブサイトです。桐生市の自然や、そこに生息している野生動物などの情報も載せています。当社のウェブサイトと相互リンクしています。なお、坂井さんからは「私の住んでいる桐生市にある山でも、ツキノワグマの生息が確認されているので、山歩きをする際には、ゴミ拾いをこころがけています。」というメッセージを頂いております。 |
|
|
|
全国の猟友会の統括する上部団体。平成15年4月16日改正された鳥獣法などの情報を掲載しています。 |
|
|
|
アースウォッチ・インスティチュート・インターナショナルは科学者、教育者、一般市民の密接な協力(パートナーシップ)によって、自然資源と文化遺産の恒久的な保存と、自然環境に対するグローバル(世界規模)な認識の拡大を推進する多国籍組織です。その国内組織がアースウォッチ・ジャパンです。 |
|
|
|
ツキノワグマの生息地でもある岐阜県内の山々や、そこに自生している山野草、岐阜や三重県内の温泉情報などがかなり濃密に紹介しているホームページです。相互リンクしています。 |
|
|
|
東北各地のローカル線を中心に紹介する鉄道民俗学、魚釣りと水辺の環境を考える環境民俗学、バーチャル・ビレッジ「くまのたいら村」から構成されたとてもユニークなウェブサイトです。 |
|
|
過去に15回様々なハチに刺された経験を持つ、スズメバチの専門家が運営している、スズメバチ情報満載のウェブページです。どうしたらスズメバチに刺されないか、スズメバチに刺された場合の対処法、スズメバチの防除方法、スズメバチによる事故例、スズメバチの生態、スズメバチの図鑑など興味深い情報が「都市のスズメバチ」にたくさん掲載されています。 | |
|
|
|
日本を代表する歴史と実績のある自然保護団体です。 |
|
|
|
キャンプや釣りを楽しむクラブ、テンカス連合のメンバーでもある製作者のウェブページ。キャンプ場や渓流釣りの紹介や、渓流魚を移植放流する際の問題点についての指摘などが掲載されています。相互リンクしています。 |
|
|
|
中國新聞社が運営している、イノシシ被害問題に特化したとても内容が濃いウェブサイトです。獣害対策に興味なる方、イノシシの被害に困っている方はぜひご覧下さい。 |
|
|
|
岩手県自然保護課のウェブページです。 |
|
|
|
ポーランドにあるカレリアン・ベアドッグのブリーダーのウェブページです。相互リンクしています。英語のページもあるので興味のある方はご覧下さい。カレリアン・ベアドッグのリンク集が充実しています。 |
|
|
|
「蚊」の専門家が運営している害虫防除技術研究所のウェブページと相互リンクいたしました。害虫防除技術研究所のウェブページでは、身の回りにいる害虫についての知識と対策について紹介しています。なお、害虫防除技術研究所は蚊調査、蚊駆除サービス、ゴキブリ駆除サービスなどを行っている有限会社モストップの研究部門です。 |
|
|
|
斜里町が運営している、知床の自然を紹介するお手伝いをしている施設です。自然解説員が知床の自然を案内してくれます。 |
|
|
|
運営:国際日本文化研究センター。日本人の精神世界の一翼を担ってきた「もののけ」「化け物」等についてのデータベース(文字データのみ)。 |
|
|
|
東アジア文化圏における「怪異」のあり方の把握や、「怪異」という言葉の持つ歴史的有用性の発見と解読などを目的とした東アジア恠異学会のホームページ。 |
|
|
|
岡山県在住の妖怪研究家・化野燐氏が運営する、妖怪の形態や性別などのデータを収集した妖怪愛好サイト。 |
|
|
|
沖縄の泡盛専門サイト。泡盛に関する情報や、美味しい泡盛を飲めるお店が紹介されています。沖縄に行く計画のある方は必見です。全国に泡盛を広げよう!相互リンクしています。 |
 当ホームページへのリンクは自由に張って下さい。
当ホームページへのリンクは自由に張って下さい。
 版画熊の解体(けぼかい)の版画/山北町立山川小学校山熊田冬季分校所蔵
版画熊の解体(けぼかい)の版画/山北町立山川小学校山熊田冬季分校所蔵
【田口洋美氏(日本狩猟文化研究所代表)の著作紹介】
●「越後三面山人記」〜マタギの自然観に習う〜 発行・農文協(ⅱ03-3585-1141)¥2,800
●「マタギ」〜森と狩人の記録〜 発行・慶友社(ⅱ03-3261-1361)¥3,914
●「フィールドワークを歩く」(須藤健一編)〜文化系研究者の知識と経験〜
発行・嵯峨野書院(ⅱ075-391-7686)¥3,605
「マタギを追う旅」〜ブナ林の狩りと生活〜
発行・慶友社(ⅱ03-3261-1361)¥3,800+税
【叉鬼山刀について紹介している書籍】
●「日本達人紀行」著者・北川広二 発行・無明舎(ⅱ0188-32-5680)¥1,800
●その他マタギ関連の書籍
●「マタギを生業にした人達」著者・野添憲治 発行・同友社 ¥1,700
●「秋田マタギ聞書」著者・武藤鉄城 発行・慶友社(ⅱ03-3261-1361)¥3,914
【マタギ関連の情報】
●『第10回ブナ林と狩人の会 マタギサミットin朝日』
●月山宣言 (マタギ達が世に問いかける名言集?)
【マタギ関連のおすすめサイト】
●山釣り/秋田・源流釣友会のサイト
阿仁マタギ・マタギの食文化・マタギの伝統・マタギ関係の書籍リストなどを掲載
http://www.asahi-net.or.jp/‾jf3t-sgwr/
トップに戻る